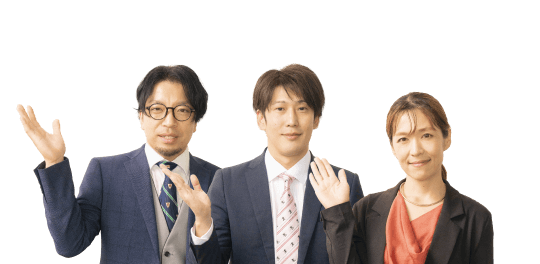「親が物忘れをすることが増えた。もし認知症になったら、お金や家はどう動かせば…?」
そんな不安を抱えたまま先延ばしにしてしまうと、いざという時に銀行口座の入出金や不動産の売却・修繕が事実上ストップし、介護や生活の判断が滞ることがあります。
そこで使われる制度が「後見制度」。
なかでも法定後見には見落としがちなリスクがあるのも事実。
本記事では、認知症で何が起きるのか、後見制度の種類と落とし穴、そして“認知症になる前”にできる備え(任意後見・家族信託)までを、実例を交えながら分かりやすく整理します。
親が認知症になると何が困るのか?
まず押さえたいのは、「困りごと」は医学的な診断名そのものよりも、法律上の“意思能力”が疑われることで発生するという点です。
意思能力が揺らぐと、次のような影響が連鎖します。
- 銀行口座が“実質”凍結状態に
家族が代理で引き出そうとしても、金融機関は本人確認や意思能力を厳格に見ます。
窓口で「ご本人の意思確認ができないためお取り扱いできません」と止まるケースは珍しくありません。
介護費や施設費の支払い、税金・公共料金の引き落とし変更など、日常の事務が滞ります。 - 不動産の売却・修繕・賃貸が動かない
実家を売却して介護費に充てたい、空き家を修繕して賃貸に出したい——いずれの契約行為ができません。
本人の署名押印や委任の意思が確認できないと、売買契約は成立しません。
結果、維持費・固定資産税だけが出続ける負担に陥りがちです。 - 各種契約・同意が無効になり得る
施設入所の契約、家のリフォーム、保険や各種解約・切替など、“同意”や“委任”が前提の手続きは一気に難易度が上がる。
家族が「良かれ」と動いても、後から無効主張されるリスクが残ります。
このように、お金も家も“動かしたくても動かない”状態に陥るのが、家族にとっての最大の痛点。だからこそ、「なる前」に備える意味が生まれます。
後見制度とは?
後見制度の目的は、判断能力が十分でない人の生活と財産を守ること。大きく分けて2種類あります。
- 法定後見
すでに判断能力が低下している状態で、家庭裁判所に申し立てて後見人を選任してもらう仕組み。後見人は司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が選ばれることも多く、財産管理・契約の同意などを代行します。誰が後見人になるか、本人・家族で自由に決められないのが特徴。 - 任意後見
本人が元気なうちに、「将来、判断が難しくなったら、この人にこういう範囲を任せる」と契約で決めておく仕組み(公正証書)。誰に、何を、どこまで任せるかを事前に設計でき、本人が認知症になってから任意後見監督人の選任を経て効力が発動します。
たとえば「不動産に関する手続きは長男へ、日常の支払いは配偶者へ」という役割分担も可能です。
両者は開始タイミングと設計の自由度が大きく違います。
次章で法定後見の“落とし穴”を確認しましょう。
法定後見の落とし穴
「裁判所が関わるから安心」と思って法定後見を選ぶと、次のポイントで思ったように動かないことがあります。
- 毎月の報酬が“亡くなるまで”かかる
後見人が専門職の場合、地域や事案によりますが月2〜5万円程度の報酬が発生するのが一般的です。
終了時期は原則“本人の死去まで”。
5年・10年と続けば総額は相当な負担です。
家族にとっては、固定費の上乗せと同義になります。 - “財産を減らさない”が最優先になりやすい
後見人の基本姿勢は「本人の財産保全」。
そのため、修繕や投資的な支出(今はマイナス・将来プラス)は慎重判断になりがちです。
例)
空き家を修繕して賃貸化
→長期的にはプラスでも短期の持ち出しが生じるため、許可が下りないケースがある。 - 家族の意思・事情が反映されにくい
「早く家を売って介護費に回したい」「親の希望だったリフォームを叶えたい」
——こうした家族の思いよりも、後見人の合理判断が優先されます。
スピード感も家族主導時と比べると落ちます。 - 一度始めたら基本的にやめられない
法定後見は一時的な委任とは違い、原則継続前提の仕組み。
状況が好転しても、直ちに終了できるとは限りません。
途中で「やっぱり家族に戻したい」は難易度が高い。 - 誰が後見人になるか選べないことが多い
裁判所が選任します。
家族が望む人物が必ず選ばれるわけではなく、関わりのない専門家になることも。
連絡・判断の心理的距離を感じるご家庭も少なくありません。
要点:法定後見は「最後の砦」。
介護や生活費の支払い、住まいの意思決定をスムーズにする観点では、“なる前”の準備(任意後見・家族信託)のほうが自由度・コスト・スピードの面で優位になりやすい。
任意後見という選択肢
任意後見は、本人が元気なうちに将来の代理人と権限を設計できるのが最大の利点です。
- 誰に任せるかを自分で選べる
家族・親族・信頼できる専門家など、本人の価値観に合う人を指名可能。家族内の役割分担も設計できます。 - 任せる範囲を細かく決められる
例)「不動産の売却・賃貸に関する一切」「日常の支払い・各種解約」「入院・施設入所の契約同意」など、具体的に列挙しておくと実務が速い。 - “準備コストは一度きり”が基本
契約は公正証書で作成。
発動時には任意後見監督人の選任費用が別途かかりますが、法定後見のような“毎月固定の専門職報酬”が前提ではない点が家計上の安心につながります(監督人の報酬は事案により発生)。 - 家族信託との相性が良い
不動産や金融資産の管理・処分の実行力は家族信託が得意。
生活全般の意思決定の後押しは任意後見が得意。両輪にすると「動かない」を避けやすい設計になります(詳細は後述)。
まとめ:任意後見は「誰に・何を・どこまで」を自分で決められる。
“なる前”に動ける人のベース設計として最有力です。
事例:司法書士が後見人に。家を売って介護費に回したいのに進まない
【背景】
母が施設入所。
認知症の診断を受け、法定後見が開始。
家庭裁判所の選任で司法書士が後見人になりました。
【家族の希望】
空き家になった実家を早めに売却し、介護費・医療費に充てたい。
【現実に起きたこと】
後見人の判断は「短期的に財産が減る(売却準備や仲介手数料、残置物処理等)」として慎重に。
許可手続き・書類整備にも時間がかかり、家族の想定より大幅に遅延。
その間も維持費・固定資産税が発生し続けました。
【教訓】
本人が元気なうちに任意後見で代理権限を設計し、家族信託で不動産の管理・処分ルートを用意しておけば、家族主導でタイムリーに意思決定できた可能性が高い。
ポイント:法定後見は「不正を防ぐ」には強いが、「スピーディに活用する」には不向き。生活と資産を“動かす”準備は前倒しが鉄則。
家族信託を併用するとさらに安心
家族信託(民事信託)は、親(委託者=受益者)が信頼できる家族(受託者)に自分の財産の管理・処分権限を契約で託す仕組み。登記簿に信託契約の内容を記載できるため、不動産の実務に強いのが特長です。
- 管理・売却の実行力:受託者が信託名義で契約できるため、売却・賃貸・修繕が止まりにくい。
- 事前設計できる自由度:どの財産を、どういう条件で、誰のために使うかを契約で細かく規定できる。
- 費用は原則“一回”:公正証書作成、登記、専門家報酬など初期費が中心(目安50万円前後〜、規模・内容で変動)。
任意後見が「生活・契約全般の意思決定を支える」のに対し、家族信託は「資産の管理・処分を確実に進める」ことが得意。併用すると、介護・医療の意思決定と資金手当ての両輪が回りやすくなります。
(※家族信託の詳説は別記事で深掘り予定)
3制度のちがいを一目で(ミニ比較表)
| 観点 | 法定後見 | 任意後見 | 家族信託 |
|---|---|---|---|
| 誰が決める | 裁判所が後見人選任 | 本人が契約で指定 | 本人が契約で指定 |
| 始める時期 | すでに“なった後” | “なる前”に契約→発動 | “なる前”に契約→即運用可 |
| 自由度 | 低い(保全優先) | 高い(範囲設計可) | 高い(契約設計可) |
| コスト感 | 毎月報酬が継続(2〜5万円/目安) | 初期+監督人費用など | 初期中心(登記・専門家費用) |
| 得意分野 | 不正防止・保護 | 生活や手続きの総合支援 | 不動産・資産の実行力 |
| 向くケース | もう判断が難しい | 事前設計したい | 実家の管理・売却など |
結論:家族信託 > 任意後見 >(最終手段として)法定後見の順に検討するのが実務上は無理が少ないことが多い。
いまからできる準備チェックリスト
- 家族で共有:親の希望(住まい・医療・資産の使い方)を言語化しておく。
- 資産の棚卸し:不動産(所在地・登記)、預貯金、保険、有価証券、貸金庫、借入の有無を一覧化。
- 代理の設計:
- 生活・契約全般 → 任意後見で“誰に・何を・どこまで”任せるか決める。
- 不動産や資産の管理・処分 → 家族信託で権限と使途を定義。
- 連絡・保管:公正証書・信託契約書・合鍵・パスワード管理方針を家族で共有。
- 専門家に一次相談:想定費用・期間・段取りを把握し、着手のタイミングを決める。
- “今日できる小さな一歩”:資産リストのたたき台作成/家族ミーティングの日程決め。
コツ:“全部決めてから動く”ではなく“動きながら詰める”。最初の一歩は、資産の棚卸しから。
まずは相談を
親が元気な今だからこそ、将来を“動かせる設計”に変えるチャンスです。
「うちのケースでは家族信託と任意後見、どちらを先に?」「実家を売る前提で、どんな条項が必要?」——状況に合わせて最短ルートをご提案します。
LINEまたはお問い合わせフォームから、お気軽に初回相談をご予約ください。短時間でも、“いま決めるべきこと”がはっきりします。