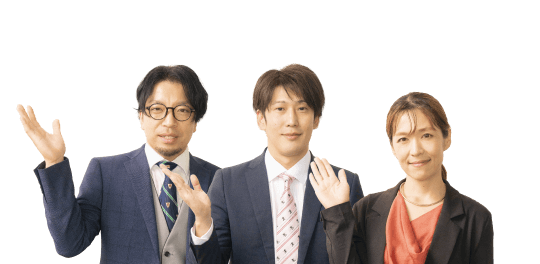はじめに
親の死去や施設入所で「実家が空き家」になるケースが増えています。
「固定資産税を払い続けている」「遠方で管理ができない」「片付けが大変で手が付けられない」――こうした声は珍しくありません。
実は、全国の空き家の約8割が「相続で止まっている」状態だといわれています。
実際、弊社の空き家調査で、
500件の空き家で400件以上が「相続発生」による空き家になっていました。
※1件1件確認しています
つまり、相続をきっかけに所有権は移ったものの、誰も住まず、活用もされず、処分の判断もできていない家が非常に多いのです。
こうした状況に対応するキーワードが「実家じまい」です。
本記事では、実家じまいとは何か、なぜ必要なのか、そして具体的な選択肢と進め方を解説します。
実家じまいとは?なぜ必要なのか
「実家じまい」とは、親世代の家を整理し、相続や将来のために処分・活用の道筋をつけることを指します。
近年この言葉が注目される背景には、以下のような要因があります。
- 核家族化と少子化:親と同居する子が減り、実家を引き継ぐ人がいない。
- 都市部への人口集中:地方の家は使い手が見つかりにくい。
- 高齢化社会:親が亡くなったり施設に入ることで、家が空き家になるケースが急増。
国土交通省の調査によれば、空き家の約8割が相続をきっかけに発生しています。
つまり、多くの人が「相続したけれどどうすればいいか分からない」と手を付けられずにいるのです。
実家じまいは、こうした「止まっている家」を動かすための第一歩といえるでしょう。
よくあるケースと悩み
実家じまいに直面する人が抱える悩みには、共通点があります。
- 県外在住で管理ができない
鍵を閉めても雑草は伸びるし、ご近所から苦情が来る。 - 売りたいけれど荷物がそのまま
親の遺品や家具が残っていて、片付けに踏み出せない。 - 解体費用や手続きが分からない
更地にすれば売れるかもしれないが、費用がどのくらいかかるのか不透明。 - 固定資産税だけ払い続けている
毎年数万円〜十数万円を支出し続け、負担が重くなっている。
こうした悩みが「判断の先送り」を招き、空き家問題が固定化していきます。
実家じまいの4つの選択肢
1. 売却する
もっともシンプルなのは「売却」です。まとまった現金化ができ、管理の手間もなくなります。
- メリット:資金が得られる、税金や管理負担がゼロになる。
- デメリット:立地や築年数によっては買い手がつきにくい。売却前に片付け・残置物処理が必要。
- 費用目安:不動産仲介手数料、残置物処理費用で数十万円。
2. 活用する(賃貸・駐車場・リフォーム)
家を残しつつ収益化する方法です。
- 賃貸に出す:家賃収入が得られるが、修繕や管理が必要。
- 駐車場にする:更地にして貸し出せば維持コストは少ないが、需要に左右される。
- リフォーム・リノベーション:初期投資がかかるものの、需要に合わせて活用可能。
3. 解体して更地にする
売却や活用の幅を広げる方法です。
- メリット:新築希望者に売りやすくなる。
- デメリット:解体費用(100〜200万円)が発生。
- 注意点:住宅があると固定資産税が1/6に軽減される特例があるため、更地にすると税額が上がる可能性がある。
4. 放置する
当面の出費を避けるために放置する人もいます。
- メリット:費用をかけずに済む。
- デメリット:資産価値の下落、倒壊や景観悪化による近隣トラブル、行政から「特定空家」に指定されれば固定資産税が最大6倍になる。
ケーススタディ
岡山に住む60代の男性は、県外にある実家を相続しました。
しかし仕事が忙しく管理ができず、そのまま放置。
数年後には庭が荒れ放題で近隣から苦情が寄せられ、草刈り業者に依頼するたびに数万円の出費。
さらに固定資産税で毎年十数万円がかかり、数年間で合計100万円以上を消費しました。
遺品整理を始めようとしたときには、残置物処理だけで100万円を超える見積もりに。
結局、売却もできず、解体費用を払って更地にしても買い手がつかない状況になってしまいました。
このように「放置」はもっともコストとリスクが大きく、早めの判断が重要だと分かります。
実家じまいを進めるステップ
- 資産・荷物の棚卸し:不動産の登記内容や残置物の量を把握。
- 相続登記を確認:2024年から義務化されており、放置は罰則の対象に。
- 方向性を決める:売却か活用か解体か、家族で話し合う。
- 専門家に相談:不動産会社や司法書士に相談し、複数の見積もりを比較。
放置リスクを避けるために
放置した空き家には次のようなリスクがあります。
- 固定資産税の増加:「特定空家」に指定されると最大6倍。
- 治安・景観リスク:不法投棄や倒壊の危険。
- 行政代執行:自治体が強制的に解体し、費用を請求される可能性。
つまり「何もしない」ことが、もっとも高くつく場合が多いのです。
まとめ
実家じまいとは、相続や高齢化で空き家になった家を整理・処分することです。
空き家の8割は相続で止まっているとされ、多くの家庭が同じ課題を抱えています。
選択肢は売却・活用・解体・放置の4つですが、放置はリスクが大きく、早めの判断が肝心です。親が元気なうちに話し合いを始めることも、立派な実家じまいの第一歩です。