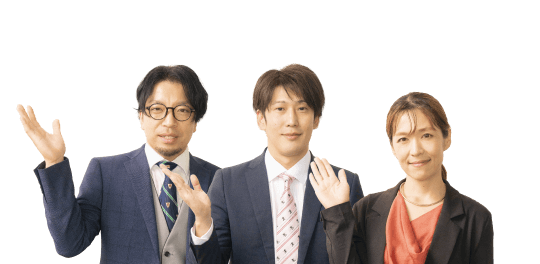はじめに
親の高齢化に伴い、「認知症になったら財産管理や相続で困るのでは?」と感じる人が増えています。調べていくと必ず出てくるのが「後見制度」と「家族信託」。
一見どちらも「親の財産を家族が管理できる制度」に思えますが、実際には大きな違いがあります。
- 後見制度は「本人を守る」ための仕組み。
- 家族信託は「財産を目的に沿って動かす」ための仕組み。
本記事では、両者の仕組み・メリット・デメリットを分かりやすく整理し、どう選べばよいのかを具体例とともに解説します。
結論の概要
- 後見制度は「本人全体の保護」が目的。裁判所の監督下で財産を守る仕組み。
- 家族信託は「財産単位の活用」が目的。契約で柔軟に設計でき、動かせる幅が広い。
- 実務では、家族信託を軸にしつつ任意後見を組み合わせると安心度が高い。
後見制度とは?
法定後見
法定後見は、すでに認知症などで判断が難しくなった時点で家庭裁判所に申し立て、後見人を選任してもらう制度です。後見人は司法書士や弁護士などの専門家になることが多く、財産管理や契約の可否を本人に代わって判断します。
特徴は次の通りです:
- 裁判所が関与するため安心感がある。
- ただし後見人は「本人の財産を減らさない」ことを最優先にするため、大きな修繕や不動産売却には慎重。
- 専門職が選ばれると月2〜5万円程度の報酬を死ぬまで支払い続ける必要がある。
任意後見
任意後見は、本人がまだ元気なうちに「将来判断できなくなったとき、この人に任せます」と契約しておく制度です。契約時に任せる範囲(預金管理・不動産売却・施設入所契約など)を決めておけます。
ただし、効力が発生するのは「判断が難しくなった」と認められた後であり、その際は裁判所から任意後見監督人が選ばれ、行動が監督されます。
家族信託とは?
家族信託は、本人(委託者)が元気なうちに、信頼できる家族(受託者)に財産管理や処分の権限を託す仕組みです。
仕組み
- 委託者:財産を託す人(親など)
- 受託者:財産を預かり管理・運用する人(子など)
- 受益者:利益を受け取る人(親が継続して受益者になるのが一般的)
例えば「この不動産を長男に任せて賃貸に出し、その収益を母の介護費に充てる」と契約で決めれば、その目的の範囲で受託者が不動産を自由に運用できます。
特徴
- 不動産や預金など、財産ごとに使い道を設計できる。
- 信託財産は「受託者のもの」ではなく「信託口」で分別管理される。
- 契約内容が登記に記録されるため、不動産売却や金融機関手続きにも対応可能。
- 契約時の初期費用は必要だが、毎月の固定報酬は基本的にない。
後見制度と家族信託の違い
目的
- 後見制度:本人の財産を守り減らさない。
- 家族信託:財産を目的に沿って使い、生活や承継に活かす。
始めるタイミング
- 法定後見:認知症などになってから。
- 任意後見:元気なうちに契約 → 発動は判断力低下後。
- 家族信託:元気なうちに契約 → 即日運用可能。
誰が決めるか
- 後見制度:裁判所が後見人や監督人を決定。
- 家族信託:契約で家族を指定できる。
コスト
- 法定後見:月2〜5万円が継続。
- 任意後見:監督人への報酬が継続。
- 家族信託:初期費用(数十万円〜)中心。
自由度
- 後見制度:裁判所の監督下で自由度は低い。
- 家族信託:契約に沿って柔軟に運用可能。
どちらを選ぶべき?
後見制度が向くケース
- すでに認知症などで判断ができない。
- 財産がシンプルで大きな運用を想定していない。
家族信託が向くケース
- 不動産を売却・修繕・賃貸して資金を回したい。
- 複数の財産を柔軟に活用したい。
- 子どもが県外に住んでいて、管理を任せたい。
実務上のベスト
- 「生活全般の判断支援」=任意後見
- 「不動産や資産の活用」=家族信託
- 両方を組み合わせると、生活と財産両面をカバーできる。
手続きの流れと費用
家族信託
- 財産の棚卸しと希望の整理
- 契約内容の設計(目的・対象・受託者・受益者)
- 公正証書で契約締結
- 不動産は信託登記、金融資産は信託口座を開設
- 運用・報告開始
費用は規模によるが、公証人費用・登記費用・専門家報酬を含めて数十万円が目安。
後見制度
- 家庭裁判所への申立てから審判まで数か月かかる。
- 報酬は月々2〜5万円(専門職が後見人の場合)。
よくある質問
- Q:受託者は自由に財産を使える?
A:使えません。信託財産は「本人の利益のために」契約で定めた目的に沿ってしか使えません。 - Q:家族信託と任意後見はどう違う?
A:任意後見は本人全体を守る仕組み、家族信託は財産ごとに活用方法を設計する仕組み。補完関係にあります。 - Q:税金面の影響は?
A:贈与や相続と異なり、受益者が本人の場合は直ちに課税されません。ただし契約内容次第で税務リスクがあるため専門家相談が推奨されます。
まとめ
- 後見制度は「本人を守る」ための公的制度。
- 家族信託は「財産を動かす」ための私的契約。
- 実務では、家族信託で柔軟に資産を運用しつつ、任意後見で生活判断を補完するのが理想的。
親が元気なうちにこそ動ける準備です。「まだ大丈夫」と先送りせず、資産と生活をどう守り、どう活用するかを話し合ってみてください。